���Ƥξ���
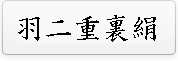
���� �����ƹ�� ��
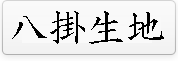
����[���ڥѥ쥹��ξ����]��Ȭ�ݡ����夲�ʥܥ�����̵�ϡ�
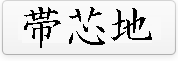
�ӿġ��������ʿ�
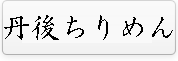
�����������
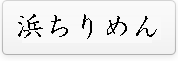
�ͤ�����������
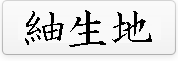
�������ݡ������ϳƼ�
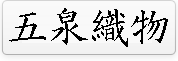
������ʪ������

���ϡ������ϡ������Ǻ�
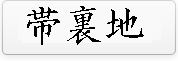
�����ѡ�������
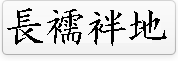
�������
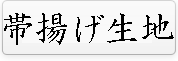
���Ȥ������ϡ�ð�����
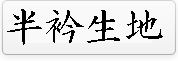
Ⱦ�� �����ϡ�ð�塢����
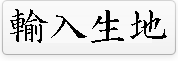
͢������������
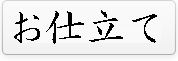
��ʪ���ӡ��� ����Ω��
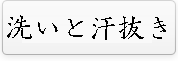
����������ʪ����˥�
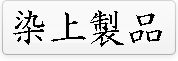
����夬��
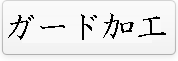
�ѡ���ȡ������å������ɡ��ù�
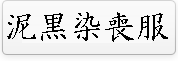
��������
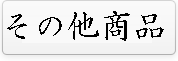
����¾��̤ʬ�ྦ��

No.1
![]() �����ѥ��륯���硼��180cmx54cm
�����ѥ��륯���硼��180cmx54cm
3,080��(��280��)

No.2
������Ⱦ�ޡ�ð�建����¥������ʬ
1,430��(��130��)

No.3
![]() �;� ������ ���ʥ� ���ζ���̾�Ų��Ӥ�
�;� ������ ���ʥ� ���ζ���̾�Ų��Ӥ�
16,500��(��1,500��)
SOLD OUT

No.4
���ӡ�̾�Ų��ӡ��������������ӿġ������ӡ���̾�Ų��Ӥ�
2,750��(��250��)

No.5
̾�Ų����ѡ���ij�����������ӿġ�̾�Ų����Ѥθ���Ǥ������Ӥ�
3,190��(��290��)

No.6
�����ѡ����ӿġ�ɱ��
2,530��(��230��)

No.7
���ˡʤ���������Ȥ������ϡ���������
25,300��(��2,300��)
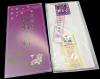
No.8
![]() ����š�ƹ�ϡ������͡�1ɥ����ʪ3��ʬ��
����š�ƹ�ϡ������͡�1ɥ����ʪ3��ʬ��
22,000��(��2,000��)

No.9
�ù��ɲ�
0��(��0��)
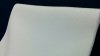
No.10
����Ⱦ�ޡ�ð�建���Ѥ껰�۽��ˡ��������ܤΤ���Ⱦ�ޡ�����ʬ����
1,430��(��130��)
SOLD OUT

No.11
���ϡ��϶ޡˡ�Ĺ����ѡ��ң��������Ĺ������������ʾ�
385��(��35��)

���� �ٿ��ʤ������䤹�Τ֡�
�֤���ΤȤ��ӡ���ʪ����ŹĹ�ξ����ٿ��Ǥ���
��ʪ������������ڤ˳ڤ��������פ�����
��Ū�ˡ��ɤ�ʪ�����ʥ֥�ˤ�����
���������Ȼפ��ޤ���
���ո�������˾��������⤪���ڤˤ�������
�ޤ���
����������ꤤ�������ޤ���
��õ���ξ��ʤ䤴���̤ϡ������ڤ�